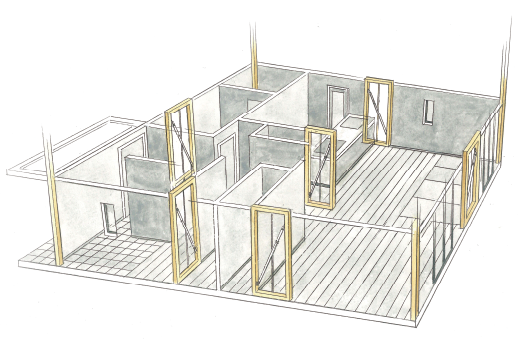- オープンハウスの耐震等級や断熱等級は?
- オプションの仕様や費用は?
ここではオープンハウスの標準仕様とオプションについて説明します。
この投稿で分かること
- 構造・性能の標準仕様
- 構造・性能のオプションや価格
標準仕様とオプション

- この内容は2024年時点のものだよ。
- 地域によって内容が異なることもあるので注意!
標準仕様
標準仕様での建物性能は下記のとおりです。
- 耐震等級:1
- 断熱等級:4
この数値は近年の法改正で義務化されている最低ランクの等級になります。
住宅ローン控除に必要な省エネ基準適合住宅の基準を満たせるため、こちらの証明書を取得することができますよ。
耐震等級1とは?
- 「震度6強~7で倒壊・崩壊しない」かつ「震度5程度で住宅が損傷しない」レベルで、大地震による住宅損傷の可能性はあります。
- 耐震等級2は1の1.25倍、耐震等級3は1.5倍の強度があり、耐震等級1とくらべ住宅損傷が少なく、補修が少なく済みます。
断熱等級4とは?
- 住宅の断熱性能の指標値で、2025年以降は断熱等級4以上が義務化されます。
- 控除や住宅補助の条件で"ZEH住宅"等をよく見かけますが、ZEHは断熱等級5以上である必要があるため、オープンハウスで長期優良住宅やZEH住宅は取得できないと思っておいたほうが良いです。
断熱材はグラスウールを採用しています。詳細は下記のサイトを参照ください。
オプション
オプションで耐震性・断熱性のレベルアップや、増床など建物本体の造作が可能です。
耐震性・断熱性
耐震性アップには、制振装置の設置と耐震等級UPの2パターンあります。
制振装置はevoltz(エヴォルツ)という装置で、わずか3mmの揺れから揺れ幅を45~55%軽減し、大きく揺れにくい建物にしてくれます。
価格は以下の通りです。※3階建ての場合 (2階建ては20万ほどやすくなるイメージ)
- 16坪≦延床面積<21坪:75.9万円
- 21坪≦延床面積<27坪:89.1万円
- 27坪≦延床面積<34坪:102.3万円
- 34坪≦延床面積<42坪:106.7万円
次に耐震等級UPの価格は以下の通りです。
耐震等級2の場合↓
- 21坪≦延床面積<27坪:66万円
- 27坪≦延床面積<34坪:82.5万円
- 34坪≦延床面積<42坪:99万円
耐震等級3の場合↓
- 21坪≦延床面積<27坪:93万円
- 27坪≦延床面積<34坪:121.6万円
- 34坪≦延床面積<42坪:150.2万円
断熱性UPには標準よりもより高性能なグラスウールにランクアップするオプションがあります。
価格は42.9万円で家全体のグラスウールをランクアップできますよ。
建物本体造作
建物本体の造作に関するオプションと価格は下表のとおりです。
| No | 区分 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外壁ふかし壁 | 外壁に凹凸を作ってデザイン性をUP。 | 8.2万円/㎡ |
| 2 | 造作ひさし | 窓の上部にひさしを作って、日差しを遮ることができる。 | 32.2万円/式 |
| 3 | 床補強 | ピアノ等の重いものをのせる床を補強して傷や痛みを防ぐ。 | 1万円/㎡ |
| 4 | ロフト増設 | ロフトを作って収納力をUP。 (ロフト用アルミ階段は9~10万円。) | 49.2万円/坪 |
| 5 | 折り上げ・折り下げ天井 | 空間を広く見せたり、空間のアクセントに効果的。 | 1.2万円/m |
| 6 | 天井下地 | シーリングファンやホスクリーンの設置に必要。 | 1.7万円/ヶ所 |
| 7 | 壁下地 | 壁付けの収納やテレビの設置に必要。 | 1.5万円/ヶ所 |
| 8 | 増床 | 建物の床・バルコニー・ビルトインの面積を増やす。 | 床:69.9万円/坪 ビルトイン:43.7万円/坪 バルコニー:49.2万円/坪 |
| 9 | 2→3階建て変更 | ※増坪や申請の費用は別 | 70.1万円/式 |
| 10 | 階高変更 | 階全体の高さを変更して、天井の高さを上げる。 | 1万円/㎡ |
| 11 | 吹き抜け | 上下層を連続させて採光を採り入れる。 | 42.4万円/坪 |
まとめ
最後に、この記事で紹介した構造・性能の標準仕様とオプションのまとめです。
まとめ
- オープンハウスの構造・性能の標準仕様は耐震等級1、断熱等級4。
- オプションで耐震性・断熱性を上げたり、本体の造作をすることができる。

いかがでしたか?
標準では最低限のランクですが、オプションでランクアップすることができますし、他のハウスメーカーと同程度のランクにしてもオープンハウスなら低価格で実現できますね。
ただし、建物の形的に耐震等級3が難しい場合があったりするなど、耐震・気密・高断熱を高レベルで求める場合は、他のハウスメーカーをお勧めします。
オプションについてもっと知りたい方はこちらにまとめてありますので、ぜひこちらの記事もご覧ください。
最後までお読みいただきありがとうございました!